ページ番号:764956983
Let`s骨活!食事から骨粗しょう症予防
骨粗しょう症とは?
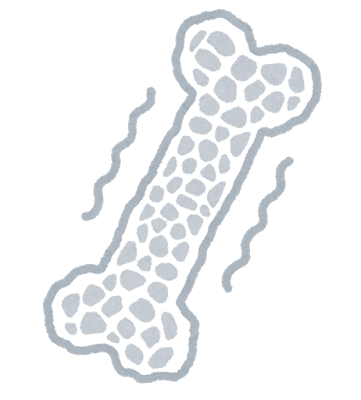
骨粗しょう症は高齢者がなる病気だと思っていませんか?
実は若い人でもなる可能性があるんです。
栄養不足、月経不順、運動不足や睡眠不足などによって、
骨密度が低下して骨粗しょう症を発症したり、骨折してしまう可能性もあります。
骨粗しょう症は女性だけではなく、男性でもなる可能性があります。
今日からコツコツ、骨粗しょう症予防の“骨活”を始めましょう。
骨粗しょう症の危険因子
生活習慣や持病の有無、遺伝などさまざまなものが影響します。
生活習慣に関しては、改善することができるので、できるところからコツコツと始めましょう。
(1)生活習慣によるもの
- やせ
- 喫煙
- アルコールのとり過ぎ(お酒の飲み過ぎ)
- 糖尿病などの生活習慣病 など
(2)生活習慣以外によるもの
- 加齢
- 閉経(早期閉経 45歳未満)
骨活、3つの要素
骨の健康には以下の3つが関わります。
取り組みやすい事から“骨活”を始めましょう!
- 運動
身体を動かすと骨に刺激が加わり、骨の強度を高めることにつながります。
安全に配慮したうえで、ウォーキングや体操、筋力トレーニングなどに取り組みましょう。
注記)過度な運動は骨折などの怪我の原因となります。ご自身の身体の状態に合わせて無理のない範囲で取り組みましょう。健康状態に不安のある方は、事前にかかりつけ医にご相談ください。
- 日光浴
日光に当たることで骨の健康に関わる栄養素、ビタミンDが体内でつくられます。 - 食事
骨の健康にはさまざまな栄養素が関わります。
本ページでは、食事について詳しく解説します。

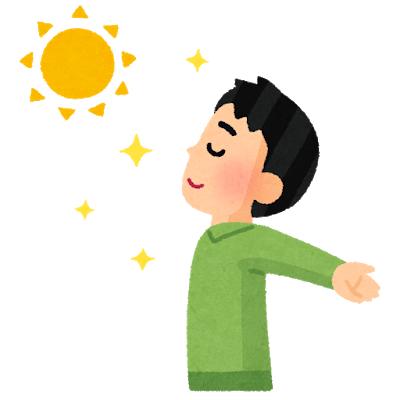
骨活~食事編~

食事におけるポイントは4つあります。
運動、日光浴と組み合わせて取り組みましょう。
保健予防課では栄養相談を行っています。気になることがある方は、保健栄養係(042-722-7996)までお電話ください。
1 食事はバランスよく

骨の健康に限らず、人の身体はさまざまな栄養素が相互に関わりあって維持されています。
食事バランスを整え、適正な体重を維持することは、骨粗しょう症だけでなく、糖尿病や高血圧症といった生活習慣病予防にもつながります。
毎食、主食・主菜・副菜を揃えることを意識して、バランスの良い食生活を心がけましょう。
- 主食
ごはんやパン、麺類などの穀類 - 主菜
肉や魚、卵、大豆製品などを使った副食の中心となる料理 - 副菜
野菜やきのこ類、海藻などを使った料理
2 カルシウムはしっかりと

骨の成分の約7割は、カルシウムを主とするミネラルで構成されています。
そのため、骨の健康を維持するためにはカルシウムの摂取が不可欠ですが、現代の日本人の多くは不足しがちです。
カルシウムを多く含む食品を積極的に摂取しましょう。
カルシウムを多く含む食品と1回使用量当たりのカルシウム量(カッコ内は1回使用量)
- 普通牛乳:198ミリグラム(180グラム)
- プレーンヨーグルト:156ミリグラム(130グラム)
- プロセスチーズ:126ミリグラム(20グラム)
- わかさぎ:360ミリグラム(80グラム)
- ししゃも:165ミリグラム(50グラム)
- しらす干し:52ミリグラム(10グラム)
- 木綿豆腐:70ミリグラム(75グラム)
- 糸引き納豆:36ミリグラム(40グラム)
- 小松菜:170ミリグラム(100グラム)
- チンゲン菜:100ミリグラム(100グラム)
1日に摂ってほしいカルシウムの量
- 18歳から29歳:男性800ミリグラム、女性650ミリグラム
- 30歳から74歳:男性750ミリグラム、女性650ミリグラム
- 75歳以上:男性750ミリグラム、女性600ミリグラム
3 骨の健康を助ける栄養素
カルシウムに加え、骨の形成やカルシウムの吸収は、たんぱく質やビタミンD、ビタミンKといった栄養素も必要です。
主食・主菜・副菜を揃えた食事を習慣的に摂っている場合には、過度な不足はあまり想定されません。
以下の食品に多く含まれているため、献立に取り入れてみましょう。
- たんぱく質:肉や魚、卵、大豆製品
- ビタミンD:紅鮭、まいわし、さんま、太刀魚、ぶり、しらす干し、まいたけ、干しシイタケ、乾燥きくらげ、卵
- ビタミンK:糸引き納豆、モロヘイヤ、小松菜、ほうれん草、春菊、菜の花、キャベツ、鶏むね肉(皮なし)、乾燥わかめ、卵
4 加工食品や嗜好品はほどほどに
カルシウムの吸収を妨げる以下の食品は、摂りすぎに注意しましょう。
(1)塩分、リン
インスタント食品やスナック菓子等に含まれます。
(2)カフェイン
エナジードリンク、コーヒー、玉露、煎茶、ほうじ茶、玄米茶、烏龍茶、紅茶、抹茶等に含まれます。
(3)アルコール
参考資料
- 厚生労働省 健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~「善方裕美先生と学ぶ骨粗しょう症予防 骨活のすすめ」(外部サイト)
- 厚生労働省 報道発表資料「『みんなで女性の健康を考えよう』特設Webコンテンツ 『骨粗しょう症予防 骨活のすすめ』公開について」(外部サイト)
- 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版」
- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
- 農林水産省ホームページ「カフェインの過剰摂取について」
